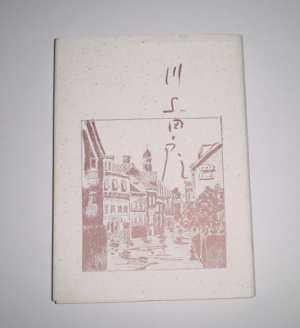
| 著書 川上四郎 | ||
| 戦前の信濃毎日新聞の建設欄 その他の投稿を編集約数百点のものを平成九年に管理人が | ||
| 自費出版した物です |
| この作品は.川端康成等監修「農村青年報告」に収録された。「鯉は曲者」「鮎」「仙造日誌」三点の一つです | ||
| 中でも.「鮎」は抜群の評価です。近々にこのページに収録します。なお[東町 唄]は親父のペンネームです。 | ||
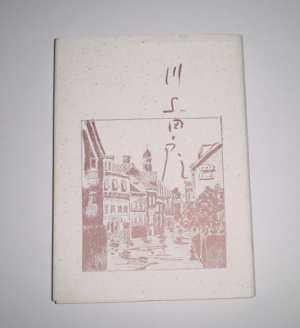 |
||
| 9月19日三点の小説の収録が終わりました 大変長い文章ですのでゆっくりとお読みください。 | ||
| なお親父のこの文章はすべて実録を素材にして書いたものです 上田 小県地方の戦前の物価 生活 理容組合 | ||
| など 貴重な資料が残されております,著書「川上四郎」は 県内の図書館 国立国会図書館などにも | ||
| 保管されておりますので 参考にされれば 幸いかと思います。 | ||
| 鯉は曲者 no1 (上) no2 (中) no3 (下) | ||
| 鮎 (1) (2) (3) | ||
| 仙造日誌 (1) |
| そして.なす術もなく.手の下し様もなく東風ふかば匂いおこせよ梅の花.といった春がまためぐり来て.水仙 | ||
| も芽ぐみ.氷の影も消え果てた頃.呼べど探せど.池の中にいたのは.尾っぽのない二寸ばかりの奴がたった | ||
| 一匹.ぽかぽかと暖かい池の端に腰をおろして.ぼく達は.もうとかげもおきだす頃だ.と大きなあくびをしてい | ||
| ると.静かな池の面を.いともうらゝかに横ぎった奴がある.それはぽちゃぽちゃと肥え太った河ねずみであっ | ||
| た。 | ||
| 戻るトップページ | ||
| 鮎 (一) 東町 唄 | ||
| 信濃毎日新聞紙上 昭和14年6月11日 | ||
| 食いつくで、見とれ。 | ||
| 興吉は、ばけつへ掌を突っ込んでかきまはした。糖味噌のような、すり餌がべっとりついた。池の面へ振った鰻 | ||
| の仔みたいなひょろながい鮎の仔は、白い腹をでんぐり返したりして、薄汚い位にまで密集し、ざわめいた。餌に | ||
| 食いついてるのだそれ見れ。興吉は得意そうに又ばけつへ掌を突っ込んだ。食うにゃ、食うが。吾作は、腹のた | ||
| しにはなるめい。と言った。それが興吉は気に食はなかった。為にならぬことがあるものか、何でも食えば、きっ | ||
| と大きくなる。興吉はそう思った。そう信じていた。だが吾作も譲らなかった。鮎には鮎の食いものがある。豚と一 | ||
| しょくたくで、鮎が育つもんかと言った。あがりを見とれ。興吉はうそぶいた。吾作にもあがりが屈託なのである。 | ||
| だから晩めしのとき女房にあたった。あがりを見とれ、みんなくたばっちまうわい。河にいる奴は水苔で、でかく | ||
| なるのだ。そいつをうどん粉や蛹なんかこね廻して、何んちょうとゆうのだ。人間だって食い物、がなけりゃ草の |
| はじめ、この仕事に手をつける時、吾作のおそれたのは漁業組合である。自分も漁業組合の役員であるし、 | ||
| 漁業組合で反対をされると手のくだしようがないのだ。資本をかけて、河川へ稚魚を放養することは全く原始的 | ||
| な方法で、むしろ無謀とさえ言える。幸、その成果が得られれば兎も角だが余りほめられた筋合のものではない | ||
| 。放養したものは、一匹残らず収魚する方法をつけねば資本の価値がない。其処で吾作は養殖をはじめた。 | ||
| 一匹に銭の稚鮎も成長すれば三匹百匁位になる。仲値でも百匁八十銭前後が相場だ。五月から八月頃まで | ||
| 僅か三四ヶ月の短期間で十倍から十数倍の利を得ることになる。水産事業が池の養殖で合理化されると漁業 | ||
| 組合員の死活問題である。だが鮎は瀬にすむものーーとゆう概念が吾作の仕事を円滑に運ばせた。むしろ | ||
| 無謀として朝笑いした。だから組合では、稚鮎の購入には共同の便宣さへはかってくれた。 | ||
| 仕事が、興吉の手に移っても、稚鮎の購入は吾作がとりはからった。それ見たことか、と三度の失敗から | ||
| 世間の侮辱をますます強くした吾作は、利害関係を超越し、興吉を通じて石にかじりついてもこの仕事を成しと | ||
| げたいと言う意地があった。意地の裏には、成功の暁は部落を一丸とした事に乗り出そうという気概があった。 | ||
| 部落の百姓の大半は漁業組合に加盟している。土地が狭盟で田圃だけではめしが食えないのだ。田の草など | ||
| は女衆の仕事にし、百姓達は、解禁になるとみんな鮎釣りにでかけた。 | ||
| 焼けつく様な暑い日である。お茶漬けをかっ込むと吾作は叉すぐ池にかけつけた。鮎は銀鱗を輝かし盛んに | ||
| 太陽に跳びあがって居た。水口には水の色が墨を流した様に密集して居た。どうだい。見事なもんじゃろう。興 | ||
| 吉は着々仕事が進んで居ることを謳歌する様に鼻をうごめかした。返事もせずに鮎の動態に擬視していた吾作 | ||
| は、駄目だっ、と唸った。これでは駄目だと、念を押した。興吉はいきなり、何が駄目で!とむかっ腹を立てた。 | ||
| 針をさした様なことでもすぐむかっ腹を立てるのが興吉の欠点だ。そのために、いつまでたっても村会議員に | ||
| なれなかった。以前、興吉は盲腸を病んだことがある。それ以来、あまりむかっ腹を立てると盲腸になるぞ!と | ||
| いうのが、部落の注意事項となっていた。 吾作の感ずいたのは、魚は水を飲むのではなく、水中にある酸素を |
| トラックへズックの水槽を備えると水を少々かい込み、氷をぶっ込んだ。汽車が来、貨車が着くと貨車を中心 | ||
| にトラックは尻を向けて並んだ。順々に貨車の水槽から水槽一個五千匹の仔鮎が、水ごてらおしあけられた。 | ||
| 貨車の水が流れ出た。あたり一面、引継ぎ作業でこねっ返し、泥沼の様になった。興吉の番である。トラックが | ||
| 動いて、ピッタリ貨車にくっつくと、うす鈍い陽がちらっと差しはじめた。水槽から水槽へ物凄い勢いで鮎諸共に | ||
| 水が押しあけられた、その中途から、突然!一匹の鮎が跳ね上がった。泥の中へ逃げ出した。さっと、隣の組 | ||
| 合員が手を出した。馬鹿っ!声と一しょに吾作は車から飛び降りた。忙しく二人の手が鮎を捕まえようとし、膝 | ||
| をついた吾作は息をはずませ、相手を睨みつけた。相手も吾作に対抗した。よせよせ。他の組合員達が二人の | ||
| 間へ割り込もうとした瞬間、泥の中でわからなくなった鮎が、一寸泥をはねた。一人がぬっと手を出してつかまえ | ||
| た。泥が飛んだ。吾作のいきなり立った泥だらけの手が、そいつの横っ面をはり飛ばした。止めろ止めろ、多く | ||
| の組合員達が三つの泥人形の真ん中へ押し合いなだれこんだ。 | ||
|
以上「鮎」をまとめました、この短編小説が親父の最高の出来と 絶賛されたものです。 |
||
| 戻る トップページへ | ||
| を示していた。その上、いはば作業上必要とする器具、化粧品類は二十割から四十割の高騰来たし、約五% | |
| から十八%の加算をしなければならぬ状態で、つまり従来の実収に四十五%からの増収を期さなければ食って | |
| ゆかれないのであった。 | |
| 顧客の平均は一戸一人とし、月一回の調髪が標準であり、今かりに、事変前月七十五円の実収を得るには | |
| 業者一軒に対し、顧客約二百五十人を必要とした。それは現在「刈込四十銭」「顔そり二十銭」を規定する料 | |
| 金の中間一人三十銭を標準に限定してのことである。従って店舗一軒に対し、二百五十戸の按分は、動かす | |
| ことの出来ぬ、決定的な生命線なのだ。 | |
| それにも拘らず、戸数二千六百戸の、この町内に同業者十六軒の存在は、店舗一軒に対し約百六十戸に | |
| しか過ぎず、これでは食えない方が道理なのだ。其処に大きな無理があった。人口が倍加するか、業者が | |
| 半滅するか、食いぬける道は二つに一つであった。だが現実は、どうにもならないのである。このうえ叉新店 | |
| がたとえ一軒でも割り込むとゆうことになれば、それだけ叉、仲間の生活は追いつめられねばならないのだ。 | |
| 言い知れぬ不安を感じるのは、おくま一人ばかりではなかった。 | |
| 尾美理髪店は最近「理容館」と看板を塗り替えて、電気バリカンも購入し、両目を一新したばかりだった。 | |
|
「ラジオも入れたってな、調子はいいかい」 |
|
| 「調子が悪いからいれたんですわ」 | |
| 景気と感違いをし、電バリの需要もあまりないらしい、尾美常吉は、炬燵でいい気持ちになって舟をこいで | |
| いた。それを、邪魔されたのが癪だ!と言わぬばかりの、素気ない挨拶である。 | |
| 「おっぱいの方も相変わらずかな」 | |
| 「商売はあてにならなくとも、あっちは月給でやすからねぇ、やめられやせんわ」 | |
| 常吉は、内職に朝夕、牛乳配達をして稼いでいた。店がひまで、労力があり余っているとゆうよりも、そうしな | |
| ければ生計が支え切れなかったのだ。彼ばかりでなく、また二足のわらじを履く者が仲間には多かった。 | |
| 「月に、いくらかな」 | |
| 「二枚半ですは」 | |
| 「二十五円!か、てぇした稼ぎだ」 | |
| たが、そうしなければならぬ日常をよく知っていたので、何とも言えなかった。 | |
| 「内職も大事だが、本職もだいじにしなよ」 | |
| 「本職が内職で、内職が本職みてえなこともありゃしてね」 | |
| 「それも仕方がねぇ。だが本業は本業、いつまでたっても本業は本業だからな」 | |
| 「げぇぶん(外聞)も大切でごわすが、四人もの餓鬼共に食いまくられては、背に腹は代えられやせんしねぇ」 | |
| 「無理もねぇこった」 | |
| 仙造は何も言わずまた表へでた。組合費の事などはおくびにも出さなかった。言い出せなかったのである。 | |
| 「何しろ税金でせぇ、丁度っこにゆかね始末なんで、ねぇ」 | |
| 追いかける様に、仙造の来た理由を察知した柔手の声が、後からかぶさって来た。たとへ腹の中では、組合 | |
| 費なんかなんちょう!とあざけっていても、腹の底にその事が沁み込んでさえ居ればそれでいい、と仙造は黙 |
| ってうなずくのだった。 | |
| 家へ帰ると、灯が着いた。 | |
| 「先っきから、待っていやした」 | |
| 新聞を見入っていた幹事の倉本がぺこりっと頭を下げた。額が大分禿げ上って顔の面積が広くなり、横の方か | |
| らかきあげた応援隊の、一本並びの薄い毛が、チックでヘバリついていた。 | |
| 「ネクタイなんかでしゃれこんで、何だね」 | |
| 「商売ですわ、今日は」 | |
| 「商売!あんたは床屋じゃろう」 | |
| 「保険屋をはじめやした」 | |
| 「また、内職かな」 | |
| 「結局は、そうなんで」 | |
| 「わしも一本、入るかな」 | |
| 「眞平ですは」 | |
| 「いけんかね」 | |
| 「棺桶を契約するような隠居なんか、駄目ですわ」 | |
| 「商売でも、駄目かね」 | |
| 「隠居は駄目でも、娘さんを一つ。すっかり契約書をこしらえて来やした、印だけ押して貰えばそれでいい」 | |
| 倉本は、黒鞄から用紙を取り出した。 | |
| 客が来たので、仙造は、見向きもせず、白衣をひっかけて、おいでなんし、と店へ出た。四五歳の女の子だった | |
| 。クロームの眼鏡をかけた痩せ形の奥さんが付き添って来、あまり見かけぬ新客だった。 | |
| 「オカッパですな」 | |
| 「ええ、なるべく明朗型にやって頂戴」 | |
| 「はあ、めろ型ですな」 | |
| 発音が一寸変なので仙造にはよく呑み込めなかったが、合槌をうち、子供を椅子に抱き上げた。刈布を巻いて | |
| 、水ブラッシュで髪を揃え、上耳あたりから力鋏を入れて線をつけた。 | |
| 「母ちゃん、おしっこ」 | |
| もずもずしていた子供が急に立ち上がった。もうすんでの所で耳を差しそうになり、仙造は思はず冷汗をかい | |
| た。おしっこをすまして叉はじめると、今度はストーブの側がいいと駄々をこね、椅子から飛び降りてしまった。 | |
| そのうちに椅子から椅子へ渡り歩いたり、しまいには客待ちのボックスへ這い上がり、どしんどしんとスプリング | |
| の反動を面白がったり、仙造は、鋏と櫛を持ったまま子供のあとを追いかけ廻し、ほとほと当惑した。 | |
| 。こうゆう客は、実に苦手なのだ。 | |
| 「仲々、お元気ですなあ」 | |
| 皮肉ともつかず、嘆声した。 | |
| 「本当に困りますの、うちでは自由主義にそだてていますんでねぇ」 | |
| 「ははあ、自由主義ですか」 |
| 奥さんのお先が知れるような気がした。 | |
| 「一時間の上もかかって金二十銭也か、むしろ迷惑ですなあ、ああゆう客は」 | |
| 倉本も、身に覚えがあるので苦笑した。 | |
| 「これも、商売さ」 | |
| 「先達も仲間が湯でこぼしていたんですが、米もあがったし、炭もあがった。物によっては金を並べても手に入 | |
| らぬし、いよいよやり切れなくなりやした」 | |
| 「わしもやりきれなくなった」 | |
| 「値上げをしてくれと、仲間からは矢攻め楯攻めですわい。刈り込み一つで米二升は買えたものが、今じゃ、 | |
| 一升と買えねぇ」 | |
| 「わしも値上げをしたくなった」 | |
| 「思い切って、何とかならぬものですかい」 | |
| 「国策じゃでな、上げるわけにもゆかねぇ」 | |
| 「床屋じゃ、闇取引もできねぇし、精一杯肉一杯の商売はつれぇこった」 | |
| そして仙造は、懸聯の指令を、先走るわけにもゆかねぇし、とっつけ足した。 | |
| 倉本は、じっと考え込んだ。そうしてまた思いだしたように、さっきの続きですがね!と別人のごとく、緊張した | |
| 面をくずした。 | |
| 「保険は、きらいじゃよ」 | |
| 「商売始めに、吝をつけられては困りやす。わっしは、人のためにすすめるんじゃごわしね、みんな自分のため | |
| ですわ」 | |
| 「教わってきたな、手を。いやにはっきりしとる。だがな、銭をしぼることよりも、持ち込むことも考えた方が、人 | |
| によろこばれるがな」 | |
| 「そこですは、誰かを紹介してくれれば、いいですわ」 | |
| 「いや、保険屋の御手伝いは御免だな。あんたも組合の役員だったら、床屋は床屋で生きることを考えるんだ | |
| な」 | |
| 然し倉本も、言われるまでもなく叉、若い時は一角の夢を描いていた。椅子を幾つも並べて、人を雇い、技術 | |
| を売り物に所謂薄利多売主義で店を繁昌させることが、随一の希望であった。叉、誰しもそれを希い、望んで | |
| いた。昔はそれでよかったのである。当時は、町内にも確か五六軒の店舗しかなく、多少は戸数も、現在より | |
| は少なくとも、それでも一軒あたり三百五十戸からの割合だった。従って、内職などをするひまもない程、店は | |
| 盛ったし、しなくても結構、商売一筋で気楽に食って行かれたのだ。 | |
| それがいつしか仲間が殖え、現在は三倍にもなった。その上、叉新店が割り込んで来る。結局顧客は分割 | |
| され、椅子を増やすどころか、一人でも労力はあり余るような結果になって、何れも夢なく昔の夢を捨てなければ | |
| ならなくなったのである。そして時局の反映は、また多くの人を、都市に転出し、丸刈りは流行る、自家用虎刈は | |
| 殖える。とどのつまりは減った仕事の、料金値上げなのだが、どっこいそれも低物価政策に押さえられて動きが | |
| とれぬのだ。 | |
| 倉本ばかりでなく、仲間の脳裡に日一日と深く去来するものは、結局、昏迷と不安の焦燥なのだ。 |
| 定休十七日夜。親睦を目的とした月例会のあと、新平は仙造と二人っきりになると、 | |
| 「いよいよ臨時総会、とゆうもんでしょうな」 | |
| と、先程の値上論の沸騰を思い浮かべて、割きれぬような苦笑をした。 | |
| 「これも仕方がねぇ。駄目と分かっていても、わし一人でみんなの気持ちを黙殺するわけにもゆかねぇしな」 | |
| 「つれぇ、しょうべぇですな」 | |
| 「これも、しょうべぇか」 | |
| へつへつと、仙造も苦笑した。 | |
| 「五銭や十銭、上がった所で楽にもなるまいよ。溺れたものは稿でも掴む!の例えじゃろ」 | |
| 「古馬穴の、穴ふさげとゆうもんですな。じきに叉、ほかの方へも穴があく。だがおらは、組合長とは叉別の | |
| 意味で、もっと困る方がいい、みんな、とことんまで追いつめられてどうにもならぬとゆう所まで,行っていまう | |
| 方が、いいと思ってやす」 | |
| 「困る方が、いいかい」 | |
| 「いい?とゆうわけでごわしねが。そうなれば、叉生き抜く方法もある」 | |
| 「それも そうだな」 | |
| 「生じつか、食ってゆかれるとゆうことが、なにかにつけて、思い切った仕事をするのに、いつも癌ですわい」 | |
| 「きびしいな」 | |
| 「おらは、もう腹をきめてやす」 | |
| 「何をきめたのかな」 | |
| 「それじゃ、めしの食い上げだ」 | |
| 滅相な!といわんばかりの面付である。 | |
| 「それから、叉新規巻き直しでお始めるんですわ」 | |
| 新平の、言う所によると、まづ現在の店舗は全部畳んでしまい、十六人の業者を一体とした一つの強固な理髪 | |
| 会社を創設しょうとゆうのである。各自は町の中から、成る可く家賃の安い、生計費の切り詰められるような、 | |
| 田圃に近い方へ一歩退却して生活をする。 | |
| 会社は改めて、設備満端の完備した、業者自身においても、勿論であるが、一般顧客に対しては特に、これな | |
| ら理想だ!とゆうような新鮮な感じを、せいぜい三ヶ所位に新設する。位置は現在の店舗のうちから、それぞれ | |
| の要所を選定してもよい。そして業者は、つまり会社員を意味するわけだが、自宅から毎日、三ヶ所の店舗で | |
| ある職場へ通勤して商売に勤務する、とゆうのである。 | |
| 具体的には、作業上における労力の等分。交替制の問題。技術上の統一。化粧品の製造及び販売部の設置 | |
| 。月給制度と扶養家族に関する事項。吉凶に対する互助政策。生命保険及健康保険の加入等。各自の生活面 | |
| においても叉、日常必需物資の供同購入。私生活の改善。健康促進と文化及教養のための施設等々。つまり | |
| 十六軒の店を三軒くらいに切り詰めた、徹底的な経営の合理化と、生活改善の実践。余剰労力の徹底的な活 | |
| 用である。床屋商売を前面に押し出しての、生活向上を意図した立案であった。 |
| 資金の問題は、全町の風潰しの協賛を得、最小限度の、いわばポケットマネーで充分足りるような、気楽に | |
| 出資の出来る程度の株式組織にし、つまり店舗と顧客を密接に結びつけて、営業能率に拍車をかける様にす | |
| る。この場合あくまでも一人は一株を原則とし、勿論業者の出資は多いほど条件は有利であるが、極力金融資 | |
| 本家に乗っ取られぬ様に警戒をせねばならぬのだった。金融資本家の手中に帰する場合になると、おそらく | |
| 業者はより以上の苦杯をなめなければならぬことは自明であった。叉そのよき意図も、そうなると必ずや喪失 | |
| する結果になるであろう。 | |
| 無口で、必要以外には、減多にものを言わぬ彼である。その心平が、ぽつりぽつりと底力のこもった声で吐き | |
| 出す立案は、やれば出来る、とゆうことでなしに、こうしなければならぬのだとゆう圧力さえも感じられ、仙造は | |
| 、異状の昂奮さえも覚えるのだった。同時に叉、この統制経済下に於いて、それは他の業態にも共通する所 | |
| の性格を持っていた。 | |
| 「だが一つこれを生かすも,殺すも、この町内に於ける、独占権の獲得如何で、またそれは業者の死活をも左 | |
| 右するものですは」 | |
| 心平は、じろりっと、仙造をみつめた。 | |
| 物も言わず、深更まで、食い入るように、時には半ば、唸るようにきき耳立てていた仙造は、今更のように | |
| 自分の歳などを振り返って見、荷が重い!と考えぬでもなかったが、じきに叉、商売一筋への情熱が、むくり | |
| あがって来、たちまちそうした気持を吹き飛ばし、血脈の躍動して来るのを、判っきりと意識するのだった。 | |
| 「裸で、ぶつかるのだ、裸で!」 | |
| 「だが真っ先に、おらはおふくろに、真っ向から反対された」 | |
| 「反対かい、おくまさんは」 | |
| 「そして頭下しに、どやされた」 | |
| ーーやり損くなったらどうする。死に際へ来て、ひぼしになるわ。 | |
| ーーじゃあ、このままなら、どうにかなるのかい。 | |
| ーーばかやろ奴。 | |
| 「とゆうわけですわ」 | |
| 「無理もねぇ。ちょくら簡単にってゆうわけには、ゆかねぇからな」 | |
| 「と言って、他人事では、ごわしねわ」 | |
| 心平は、冷えてきた炬燵やぐらをぐっと力強く握りしめた。 | |
| 「冥土の土産が、叉殖えたかな」 | |
| 仙造も、また脂汗を滲ませて、しっかりやぐらの足を、握っていた。 | |
| 戻る→top | |
| |